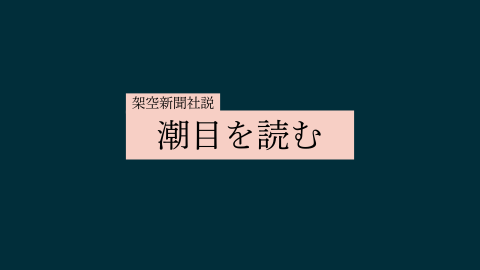私はかつて教育公務員として教育現場で働いていた。 就職活動においてなんとなく教育業界を選んだが、改めて公費の使われ方への違和感、日本の教育の課題、そして教員の質のばらつきを感じるようになった。 退職した理由は別にあるが、これらの問題を目の当たりにすることは精神的に負担が大きかった。
まず、公費の使われ方について。 公立学校で働いていたため、すべての経費が市県民の税金でまかなわれていることは当然のことだった。しかし、財源不足を訴えながらも、使途が疑問に感じられるケースが多かった。 例えば、校舎の老朽化が進み、雨漏りがひどく、改修や建て替えが必要とされながらも、優先順位が低く後回しにされていた。その一方で、特定の設備だけが急に新設されるような場面もあった。 ある年、普通校に障害のある生徒が入学することになり、そのためにおんぼろ校舎にピカピカのバリアフリートイレが設置された。もちろん、公務員は「全体の奉仕者」であるので、すべての生徒が快適に過ごせる環境を整備することは重要だ。しかし、校舎全体の老朽化が放置される中で、局所的な改修に資金が投じられることには疑問を感じた。障害のある子供は設備が整っていて専門知識を持った教員がいる特別支援学校に行ったほうが快適に過ごせるとも思う。
次に、日本の教育現場の課題について。 晩婚化の影響で、親の年齢層が高くなり、子どもを過保護に育てる傾向が強まっている。その結果、学校に対するクレームも増加し、少し注意をしただけでも抗議が入るような状況だった。生徒の中には、困難に直面するとすぐに逃げてしまう、精神的な耐性が低い子どもも見られるようになった。こうした状況を助長したのは、過度に干渉する一部の保護者の影響が大きいと感じる。
さらに、教員の質について。 教員採用試験の倍率が低下し、優秀な教員がいる一方で、経験や資質が十分とは言えない教員も増えている。また、学校の職員室は年功序列が色濃く、若手教員は雑務をこなすことが当然のように求められる。例えば、朝早く出勤し、先輩教員のコーヒーを用意し、職員室の掃除をするのが慣習となっていた。こうした旧態依然とした環境では、新しい教育の在り方を模索することが難しい。
加えて、教員の多くは「学校を出てそのまま教員になった」人が多く、社会経験が乏しいまま教育の現場に立っているケースが多い。親が教員だったから自分も教員になったという「世間知らず二世」も一定数存在する。教員は上っ面のきれいごとばかりを主張したがり、やたらと「夢!」「希望!」と言うが、ビターな社会では「現実」「必要悪」もある。彼らの中には、一般的な社会の仕組みや企業の実態を理解しないまま教育を行っている人もおり、その影響が子どもたちに及ぶことを懸念していた。
しかし、学校がすべてではない。子どもたちは、学校の授業だけに頼るのではなく、自分で学びの場を広げることが重要だ。「なぜ?」と考える力を養い、新聞や書籍を通じて多様な意見に触れることで、世の中をより深く理解することができる。 また、学校外での体験活動や異業種の大人との交流を増やし、社会のリアルな一面を学ぶ機会を持つことも大切だ。例えば、職業体験やボランティア活動を通じて、実際の社会の仕組みを学ぶことは、教室の中では得られない貴重な経験となる。
教育現場には課題が多いが、子どもたちが自ら学び、世渡りの力をつけることで、より良い未来を築くことができるのではないか。